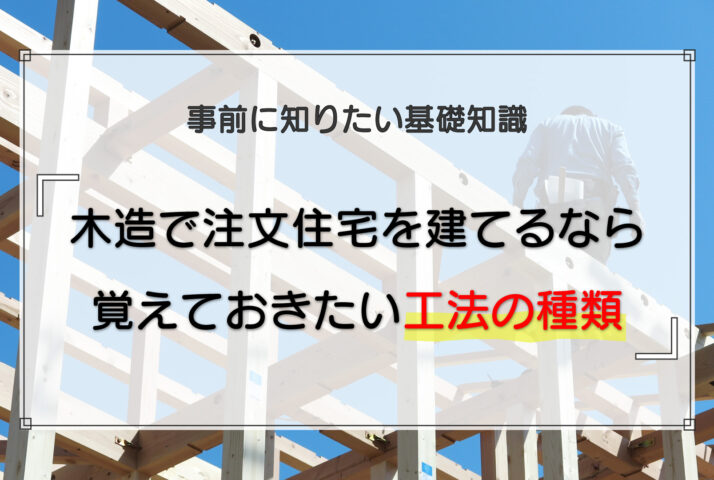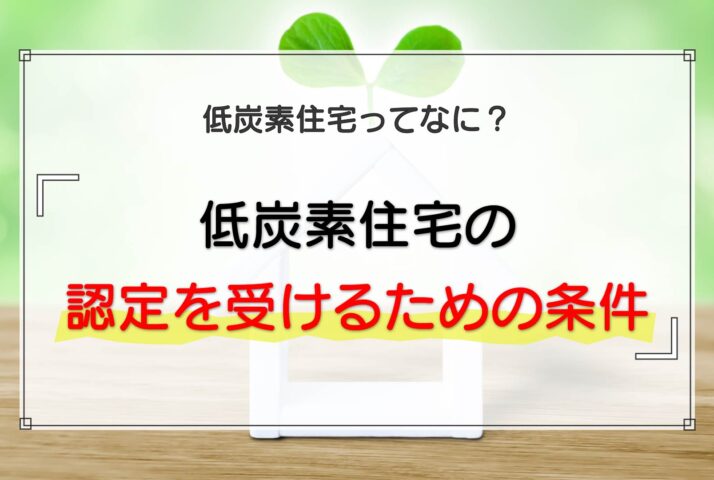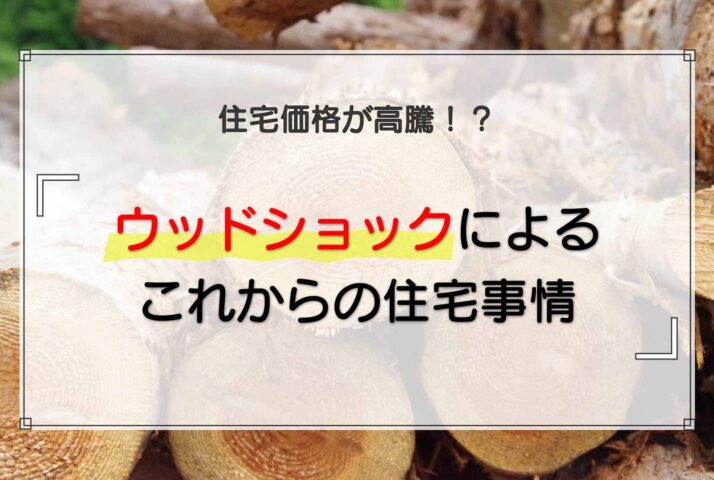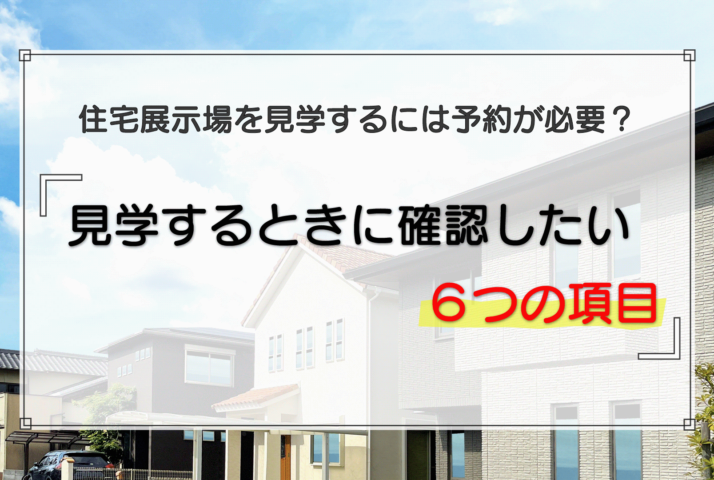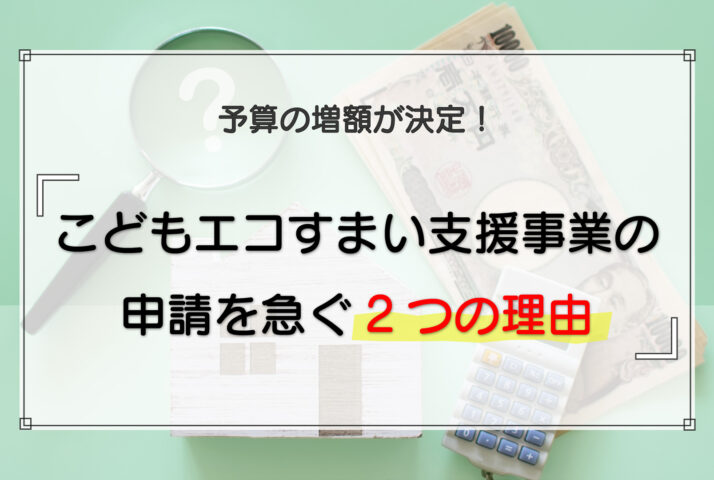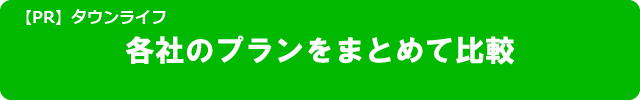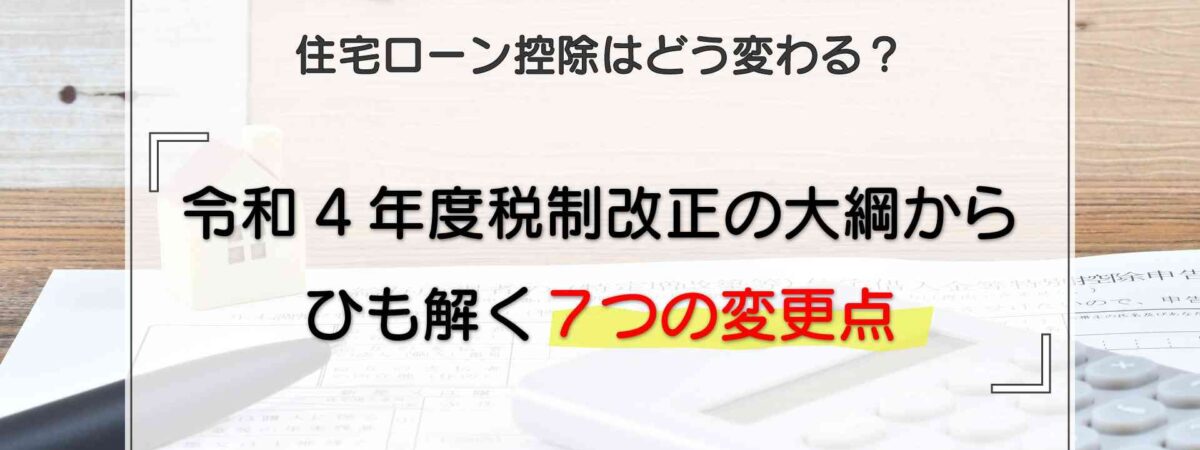
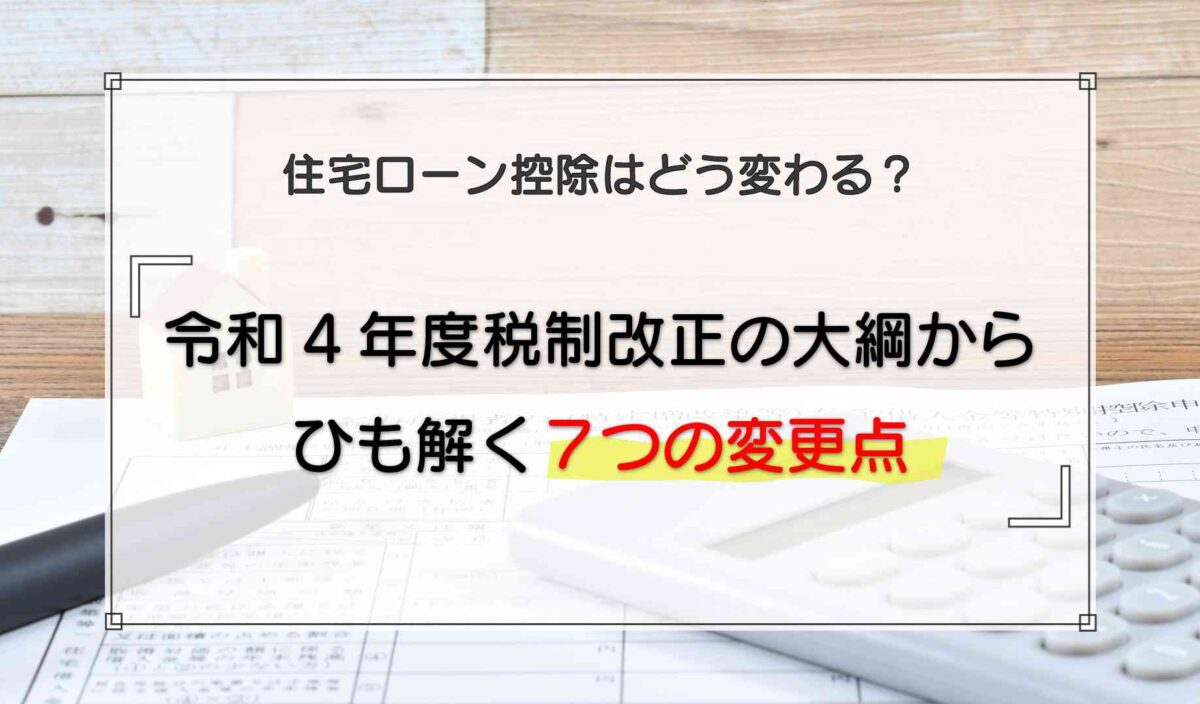
住宅ローンを利用して一定の要件を満たした住宅の新築やリフォームすると使える住宅ローン控除。2021年12月24日に「令和4年度税制改正の大綱」が閣議決定され、2022年以降の方針が明示されました。
そこで今回は、2022年の住宅ローン控除が2021年と比べてどのような変更があるのか詳しく解説します。住宅ローン控除の概要や確定申告の必要性についても解説していますので、はじめて住宅取得をする方やこれからリフォームが控えている方は、ぜひ参考にしてください。
この記事で学べるコト
- 住宅ローン控除とは何かがわかる
- 2022年の住宅ローン控除は何が変わったかがわかる
- 住宅ローン控除の適用を受けるための要件がわかる
目次
※2022年度の住宅ローン控除は、「まとめ」で一覧にしています。すぐに知りたい方は、まとめまでスキップしてください。
1.住宅ローン控除とは?所得税や住民税から一定期間、控除を受けられる制度
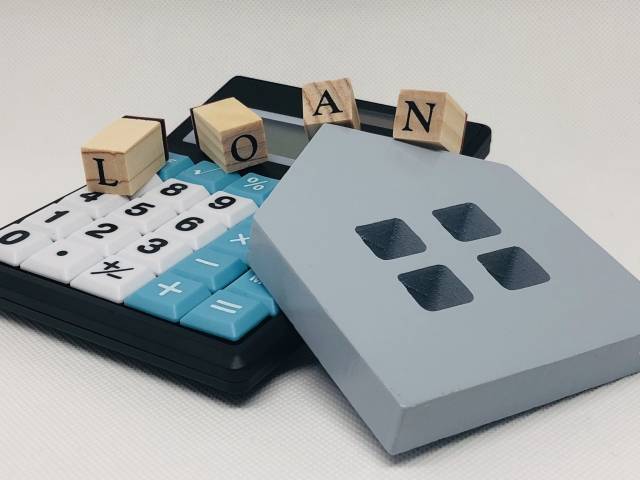
多くの方は、住宅の購入やリフォームをする際に住宅ローンを利用します。
住宅ローン控除とは、一定の住宅購入やリフォームなどで利用した住宅ローンの「年末時点の借入残高」に応じて一定の要件を満たせば、納税した所得税や住民税から一定期間、控除を受けられる制度です。つまり、一部のお金が戻ってきます。
契約者にとって負担が大きい住宅の費用ですが、住宅ローン控除をうまく活用することで、購入や工事にかかる費用負担を軽減できます。
ただし、住宅ローン控除の制度は、しばしば改正されています。本記事のタイトルにあるように「令和4年度税制改正の大綱」で2022年以降の動きが明示されました。
2.令和4年度税制改正の大綱で住宅ローン控除はどう変わる?7つの変更点

税制改正大綱とは、その年の税制改正をどのように進めていくか、政府として方針をまとめた骨組みのようなものです。
不動産以外にも自動車税や法人税など、さまざまな税にかかわる改正がまとめられています。この税制改正は毎年、年末ごろに閣議決定して翌年の方針を示しています。
2022年以降の住宅ローン控除については、令和4年度税制改正の大綱が2021年12月24日に閣議決定されました。「令和4年度税制改正の大綱」によると、住宅ローン控除に関する改正は、主に次の7つです。
- 住宅ローン控除を適用する住宅性能が細分化
- 住宅の性能によっては借入限度額が引き下げ
- 住宅ローンの控除率が引き下げ
- 控除期間が13年に再延長
- 控除対象者の所得要件が引き下げ
- 中古住宅の築年数の要件が廃止
- 住民税による控除の限度額が引き下げ
2022年以降の住宅ローン控除はどのような変更が加わるのか、2021年と比較しながら詳しく見ていきましょう。
2-1.住宅ローン控除を適用する住宅性能が細分化
2022年の住宅ローン控除では、控除対象となる住宅性能が細分化されました。昨今、日本国内で話題となっているカーボンニュートラル社会の実現のため、性能の高い住宅を増やす目的があるからです。
2021年と2022年の住宅性能の比較は次のとおりです。
| 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 住宅性能 | 認定住宅 | 認定住宅 |
| それ以外の住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | |
| 省エネ基準適合住宅 | ||
| それ以外の住宅 |
2021年までは「認定住宅かそれ以外か」の2つで分類されていましたが、2022年からは「認定住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」「それ以外の住宅」と、住宅ローン控除を適用する住宅性能を4つに細分化しています。
細分化により、認定住宅以外の省エネ性能を有する住宅にも控除の恩恵を与えることで、省エネ住宅のストックを増やす狙いがあると考えられます。
住宅ローン控除の認定を受けるための基準は次のとおりです。よくある質問ですので覚えておくと良いでしょう。
ZEH水準省エネ住宅:断熱等級5かつ一次エネ等級6の性能がある住宅
省エネ基準適合住宅:断熱等級4以上かつ一次エネ等級4以上の性能がある住宅
2-2.住宅の性能によっては借入限度額が引き下げ
住宅ローン控除を適用する住宅性能を細分化したことにより、住宅性能ごとに借入限度額も細かく金額が設定されました。「新築で住宅を取得するか」「中古住宅の取得なのか」でも借入限度額は異なります。それぞれの借入限度額は次の表のとおりです。
| 住宅性能 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入限度額 | ||||||
| 新築 | 認定住宅 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,000万円 | 4,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,500万円 | |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 4,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| それ以外の住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 ※2023年12月31日までに建築確認を受けている |
2,000万円 ※2023年12月31日までに建築確認を受けている |
|
| 中古住宅 | 認定住宅等 (ZEH水準省エネ住宅 ・省エネ基準適合住宅を含む) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| それ以外の住宅 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
2022年に住宅性能が細かく分類されたことにより、これまでメリットが少なかったZEH水準の省エネ住宅は借入限度額が引きあがりました。一方、それ以外の住宅については、最大4,000万円の控除が受けられていましたが、3,000万円までの控除となっています。
上表からもわかるとおり、2024年以降の住宅ローン控除の限度額は500万円~1,000万円下がる見込みです。住宅購入を検討されているのであれば、早めに検討を始めるといいかもしれません。
また、2024年以降に建築確認を受けて新築する住宅が住宅ローン控除を適用するには、一定の省エネ基準を満たすことが条件となっています。2024年以降は、一定の住宅性能を満たさなければ住宅ローン控除が適用されないので注意が必要です。
2-3.住宅ローンの控除率が引き下げ
2021年は1%の控除率でしたが、2022年の改正では控除率が0.7%引き下げられました。
| 2021年 | 2022年~2025年 | |
|---|---|---|
| 控除率 | 1.0% | 0.7% |
住宅ローンの控除額は、年末時点の借入残高から控除率を掛けることでその年の控除額が算出できます。
住宅ローン控除額=年末時点の借入残高×控除率
ただし、前述で紹介しているとおり、住宅ローン控除には借入限度額が設定されています。限度額を超える金額は控除されません。
また、上記で計算した控除額の満額が戻ってくるわけではありません。その年に納税している所得税や住民税以上の控除は受けられないためです。
控除率が変更になったことで、住宅性能別の最大控除額は次のようになりました。
| 住宅性能 | 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 最大控除額 | |||
| 新築 | 認定住宅 | 600万円 (控除期間13年適用) |
455万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 480万円 (控除期間13年適用) |
409.5万円 | |
| 省エネ基準適合住宅 | 480万円 (控除期間13年適用) |
364万円 | |
| それ以外の住宅 | 480万円 (控除期間13年適用) |
273万円 | |
| 中古住宅 | 認定住宅等 (ZEH水準省エネ住宅 ・省エネ基準適合住宅を含む) |
300万円 | 210万円 |
| それ以外の住宅 | 200万円 | 140万円 | |
2-4.控除期間が13年に再延長
住宅ローンが控除される期間は10年が通常です。2022年の改正では10年から13年に延長されることになりましたが、延長といっても再延長です。
住宅ローン控除が13年に延長されるようになったのは、2019年10月1日です。消費税が8%から10%の増税にともない、消費税10%の住宅を購入する場合には、13年の延長措置が適用されました。
参考:財務省:「平成31年度税制改正の大綱の概要」
当初、延長期間は2019年10月1日~2020年12月31日としていましたが、新型コロナウイルス感染症によって与えられた経済への影響を転換・好循環へと変えるため、2021年も13年延長していました。
つまり、デフォルトの10年と比較すれば、還元される期間が3年増えていますが、2021年と比較しても期間が増えた印象は少ないでしょう。
| 2021年 | 2022年~2025年 | ||
|---|---|---|---|
| 新築 | 控除期間 | 13年(デフォルトは10年) | 13年 |
| 中古住宅 | 10年 | 10年 | |
中古住宅の控除期間は10年の据え置きなので注意が必要です。
2-5.控除対象者の所得要件が引き下げ
2021年までは控除対象者の所得要件を3,000万円以下と定めていましたが、今回の改正によって、2,000万円以下に所得要件が引き下げられました。
| 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 所得合計金額 | 3,000万円以下 | 2,000万円以下 |
上記は、あくまで所得合計2,000万円以下です。年収ではないので注意しましょう。所得金額は、住民税納税証明書や納税証明書で調べられますので、確認しておくと良いでしょう。
また、取得する住宅の広さ(床面積)によっても所得要件が異なります。床面積が40㎡~50㎡未満の住宅の場合は、所得要件がさらに低く1,000万円以下となっています。
所得税に関係する所得の合計が1,000万円を超えてしまうと、その年の住宅ローン控除は適用されません。
2-6.中古住宅の築年数の要件が廃止
2021年までは中古住宅で住宅ローン控除の適用を受けるには、築年数の要件を満たす必要がありました。しかし、2022年の改正で築年数による要件が廃止され、新耐震基準に適合している住宅であれば控除を受けられるように変更されました。
登記簿上にある建築日付が「昭和57年1月1日以降」であれば、新耐震基準に適合している住宅としてみなされているため、1982年以降の住宅であれば住宅ローン控除の対象となります。
| 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 築年数の要件 | 木造:築20年 耐火構造:築25年 |
1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅 |
つまり、1981年以前の建物を購入する際には、住宅ローン控除が適用されませんので、覚えておきましょう。
2-7.住民税による控除の限度額が引き下げ
前述でも軽く紹介しましたが、住宅ローン控除は納めた所得税・住民税から控除される制度です。具体的には、住宅ローン控除額(年末の借入残高×控除率0.7%)から所得税額を引きます。所得税額から引いて控除できなかった分を住民税から控除する仕組みです。
この住民税から控除できる金額には上限が設けられています。今回の改正によって、2022年の控除額が減少しました。
| 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 住民税による控除限度額 | 前年度の課税所得×7% (最大136,500円) |
前年度の課税所得×5% (最大97,500円) |
2021年は住民税から最大で136,500円の控除が適用されていましたが、2022年は限度額が97,500円と年間で換算すると39,000円のダウンです。
3.住宅ローン控除の適用を受けるための要件5つ
住宅ローン控除を受けるには、第2章「2.令和4年度税制改正の大綱で住宅ローン控除はどう変わる?7つの変更点」であげた変更点の他にも、満たさなくてはいけない要件が5つあります。
5つの要件は次のとおりです。
- 自ら居住する住宅であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 店舗併用住宅や賃貸併用住宅の場合は、自らの居住スペースの床面積が1/2以上であること
- 床面積は50㎡以上(新築の場合は2023年までに建築確認を受けていれば40㎡~50㎡未満の住宅も可。ただし、所得要件が1,000万円以下となる)
- 引き渡しや工事完了から6カ月以内に入居すること
新築やリフォームをする際には、上記要件にも当てはまっているか確認しておきましょう。
4.住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要
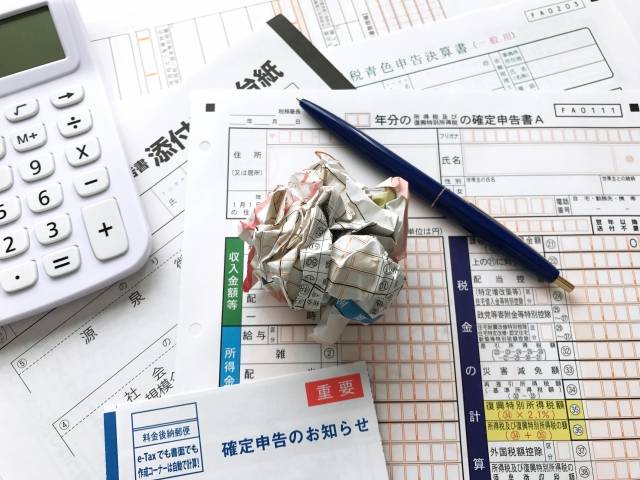
控除をうけるための要件を満たして住宅購入やリフォームすれば住宅ローンが適用されます。しかし、なにもせずに控除額が振り込まれるわけではありません。住宅ローン控除を受けるには必ず申請をしなければ控除を受け取れませんので注意が必要です。
住宅ローン控除を受けるには、住宅を取得したその年に税務署へ確定申告をします。確定申告も必要書類と申告書を記入して提出すれば完了しますので、難しく考える必要はありません。
確定申告で必要な書類は次のとおりです。
- 源泉徴収票等(原本)
- 住宅ローンの年末残高等証明書(原本)
- 工事請負契約書または売買契約書(コピー)
- 土地・住宅の登記事項証明書(原本)
- マイナンバーカード(写し)
認定住宅等の一定の性能を有する住宅の場合には、その住宅だと証する書類が追加で必要です。また、補助金などの交付を受けている方は「補助金決定通知書など」住宅購入で贈与を受けた方は「贈与税申告書など」も準備しましょう。
会社員の方であれば、1年目の確定申告をしておけば2年目以降は会社の年末調整で控除を受けられます。
国税庁のホームページにも確定申告特集のページがあります。自宅からでも案内に沿って情報を入力していくだけで確定申告書が作成できますので、確定申告が不安な方は事前に確認してみると良いでしょう。
まとめ
住宅ローン控除は、新築の購入やリフォームなどで利用した住宅ローンの年末残高に応じて、納税した所得税や住民税から控除を受けられる制度です。控除額や期間は、購入する住宅の種類や性能によって細かく定められています。
2022年の改正では主に7つの変更がありました。
- 住宅ローン控除を適用する住宅性能が細分化
- 住宅の性能によっては借入限度額が引き下げ
- 住宅ローンの控除率が引き下げ
- 控除期間が13年に再延長
- 控除対象者の所得要件が引き下げ
- 中古住宅の築年数の要件が廃止
- 住民税による控除の限度額が引き下げ
この7つの変更点から、2022年の住宅ローン控除は次の表のようになります。
| 新築 | 中古 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | それ以外の住宅 | 認定住宅等 (ZEH水準省エネ住宅 ・省エネ基準適合住宅を含む) |
それ以外の住宅 | |
| 借入限度額 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 |
| 控除率 | 0.7% | |||||
| 控除期間 | 13年 | 10年 | ||||
| 最大の控除額 | 455万円 | 409.5万円 | 364万円 | 273万円 | 210万円 | 140万円 |
| 所得要件 | 2,000万円以下(床面積:40㎡~50㎡未満は1,000万円) | |||||
| 築年数の要件 | – | 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅 | ||||
| 住民税による控除の限度額 | 前年度の課税所得×5%(最大97,500円) | |||||
「どこの建築会社に相談しよう?」
業者選びを始めるなら
各社のプランを無料で比較!
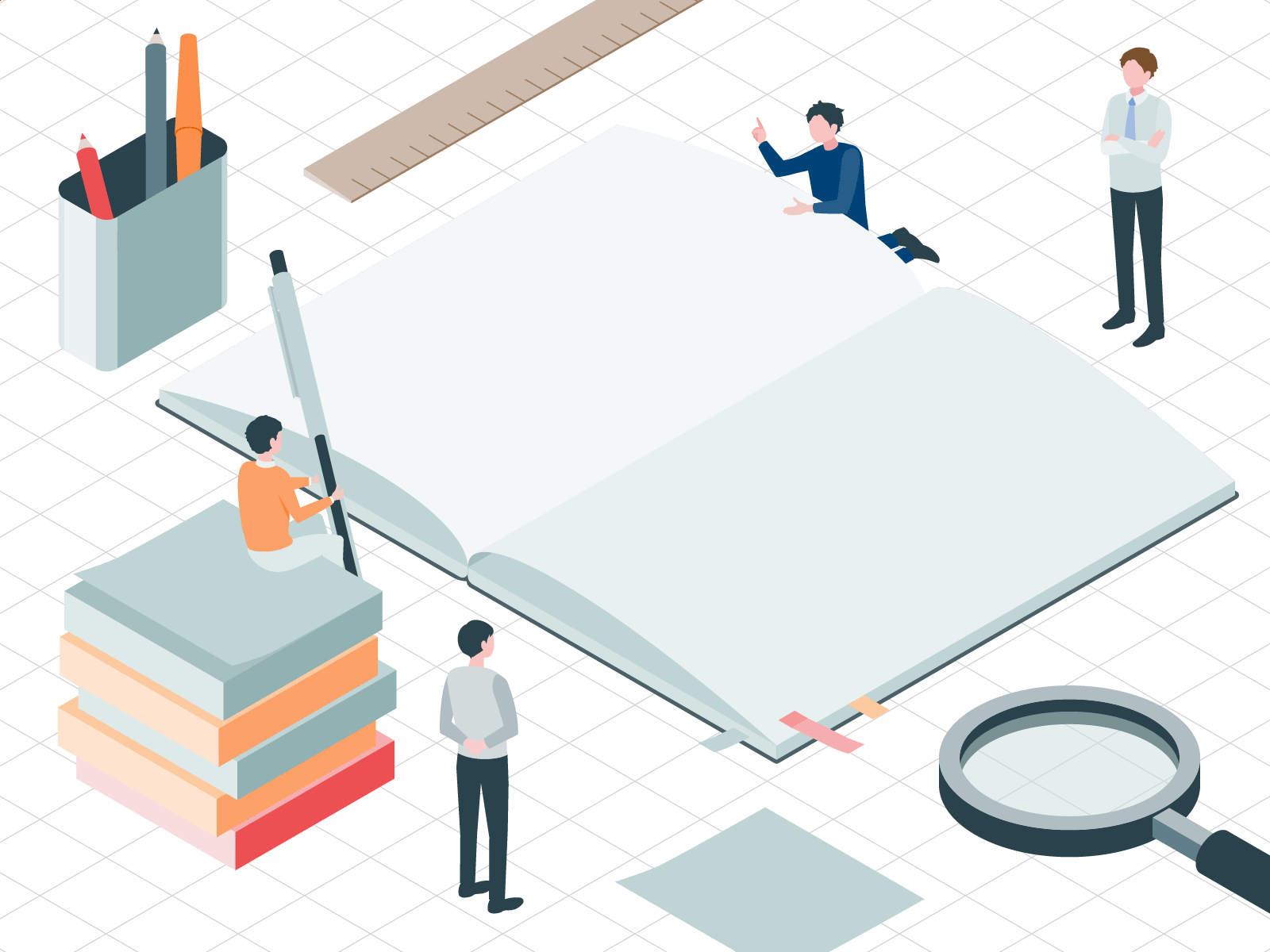
- 注文住宅は一生に一度の大きな買い物。絶対に失敗したくない!
- 家族の理想を叶えてくれる建築会社が判断できない。。。
- オシャレな写真を参考にしてるけど、取り入れたいプランがありすぎる!
ひとつでも当てはまるなら、
複数社のプラン比較がおすすめです
家族の理想をカタチにできる注文住宅。
理想を実現するためには、優れたパートナー選びが重要。
しかし、自分とマッチする建築会社を探すためには
各社のモデルハウスを見学
問い合わせフォームからカタログ請求
と、一社一社調べるには時間も手間もかかる...
そこで、すきま時間の情報収集で利用してほしいのが
「タウンライフ家づくり」です。
タウンライフ家づくりでは、家づくりで大切な「資金計画」から「間取り」など、あなたの要望にあったプランをまとめて比較できます。
もちろん利用は無料!
提案してくれた企業と契約しないといけない縛りもありません。
これから理想の家づくりを始めるなら、まずは自分にピッタリな間取りプランを把握しましょう。