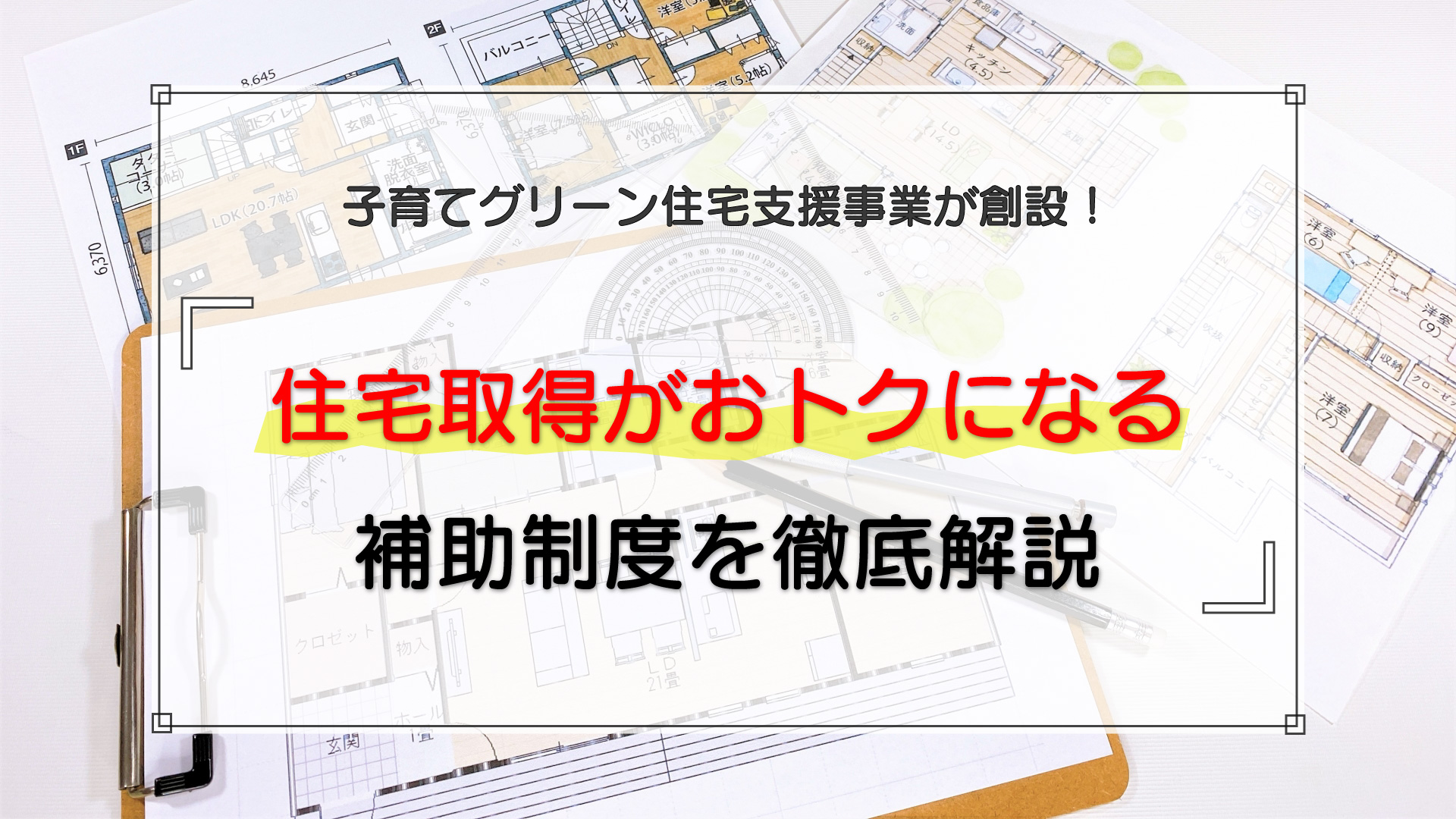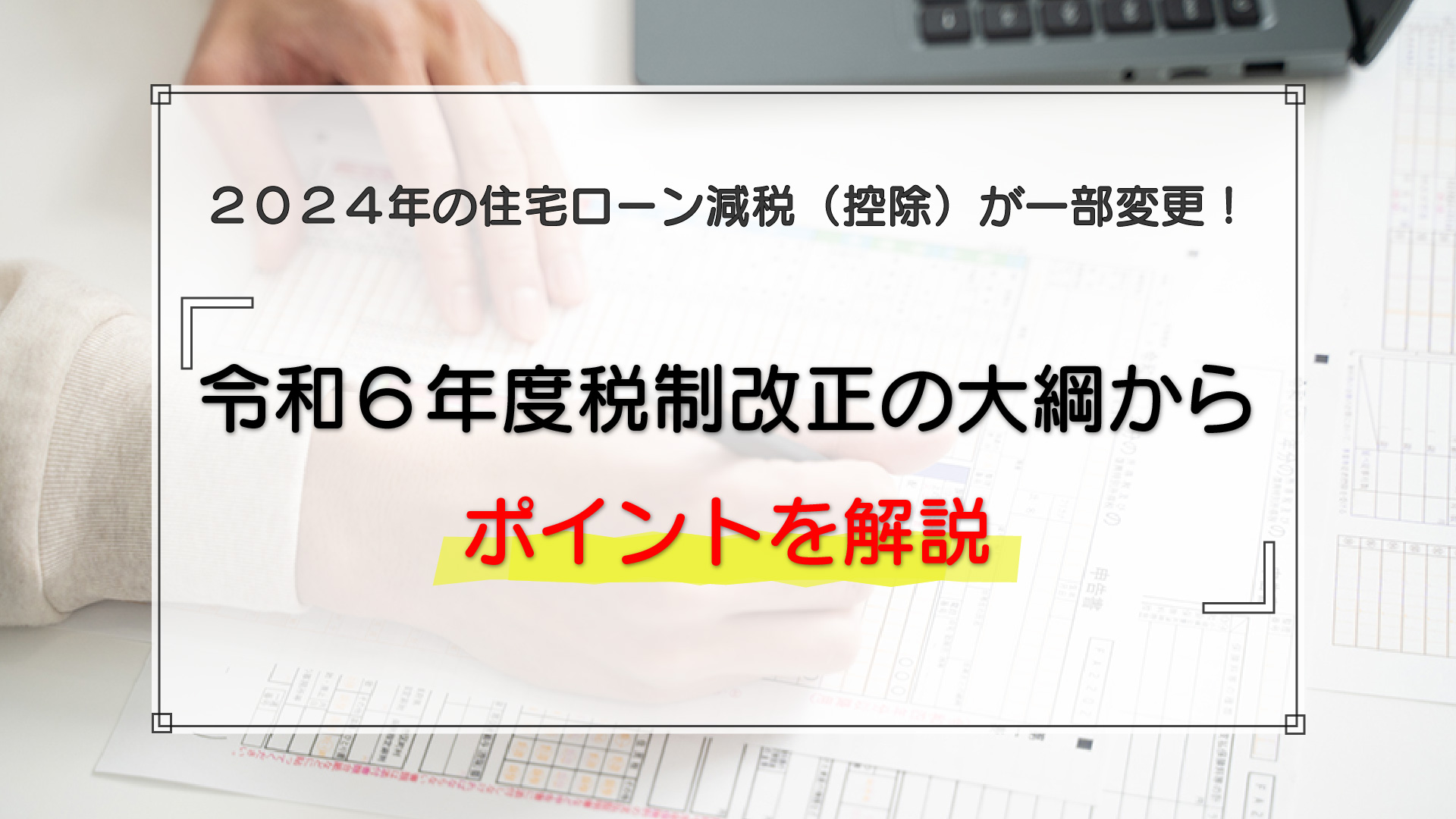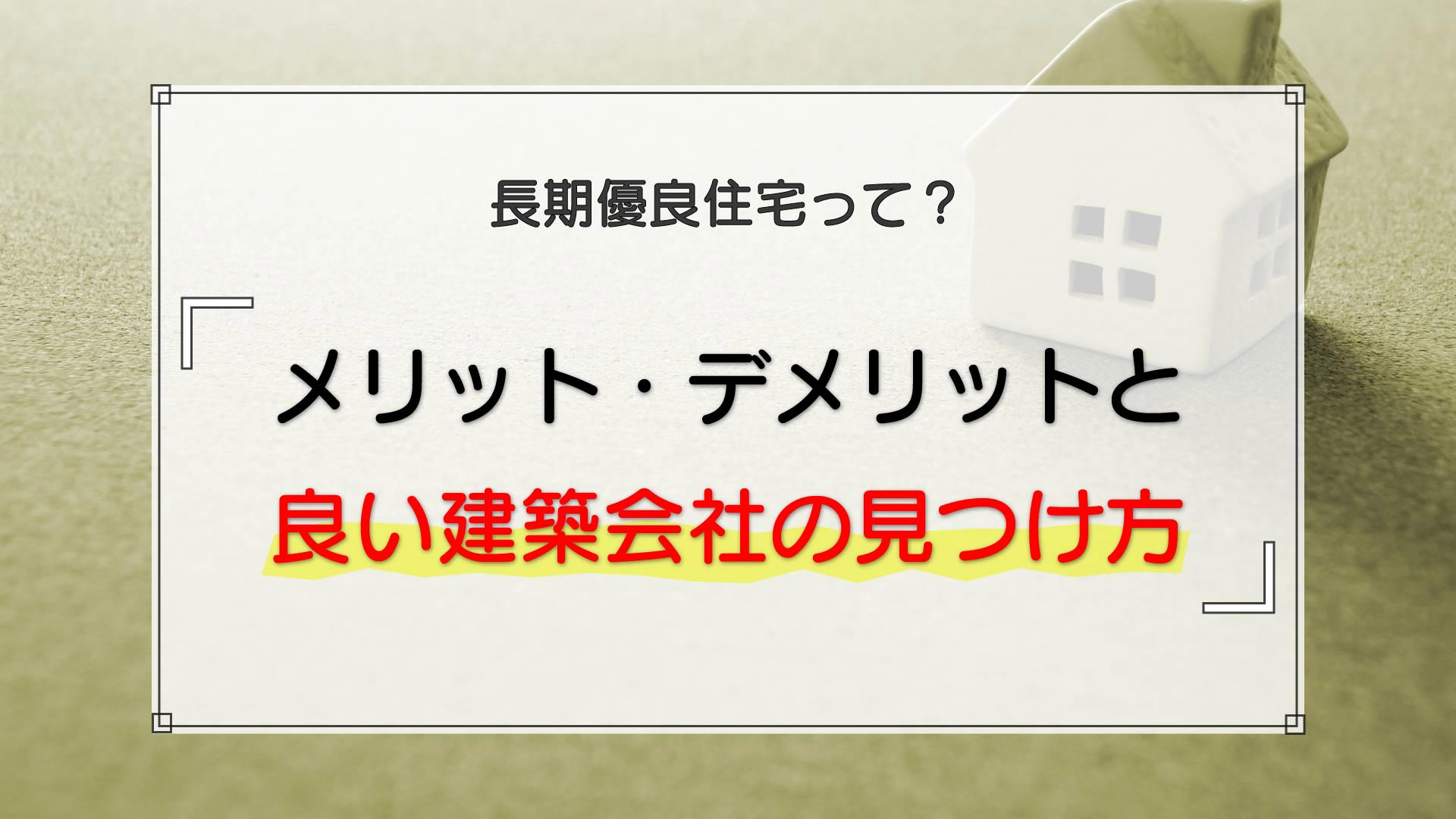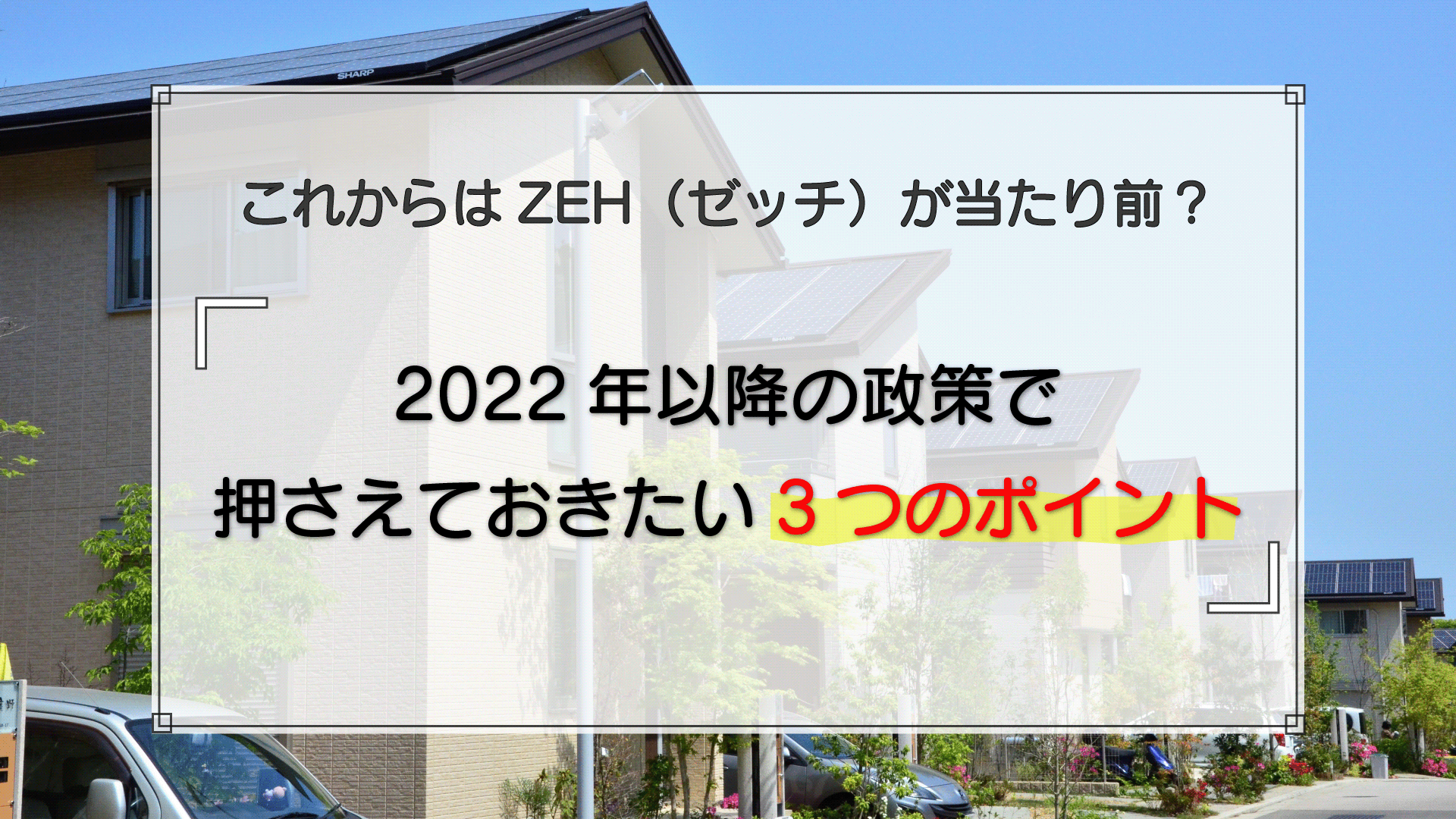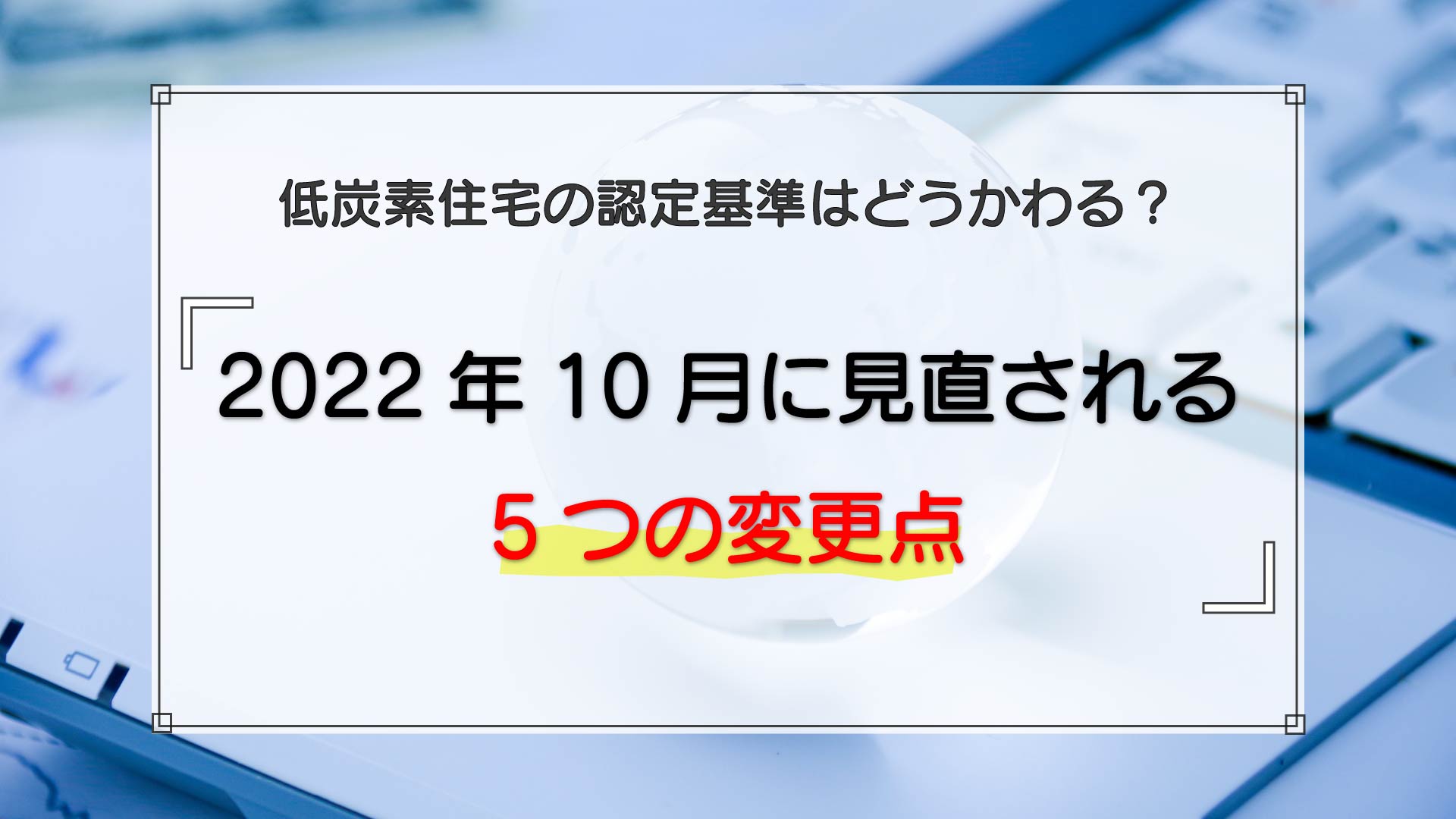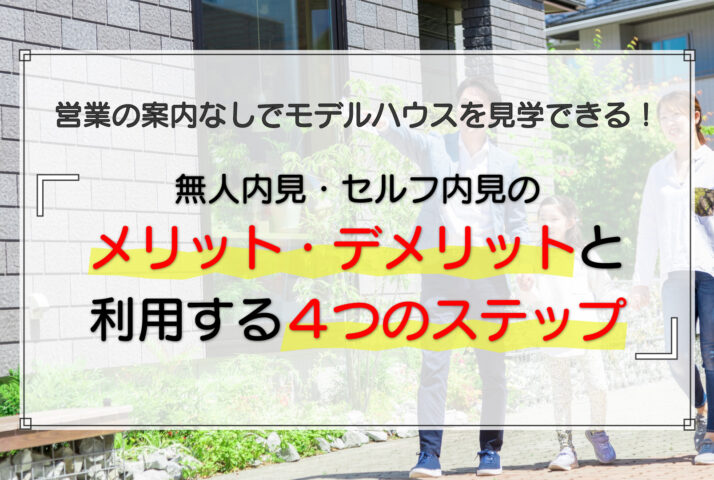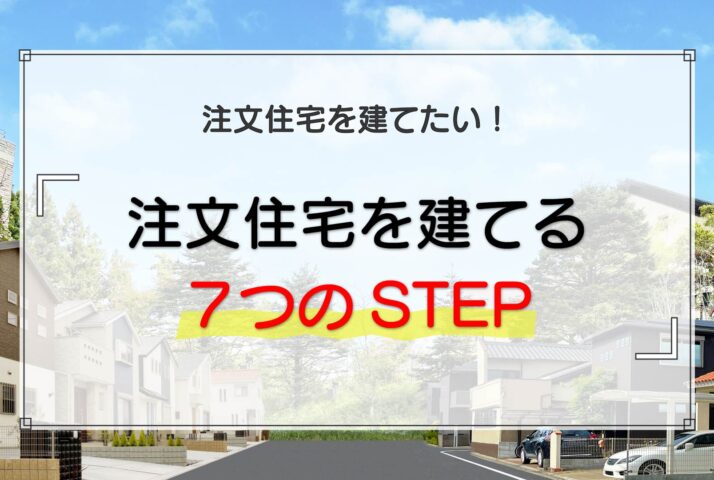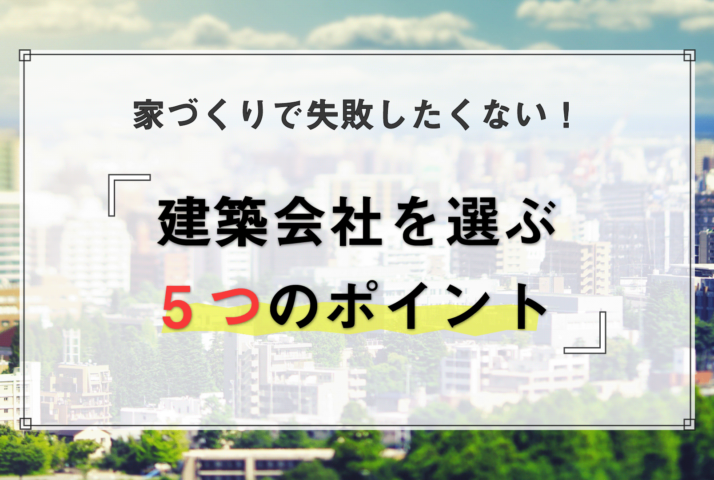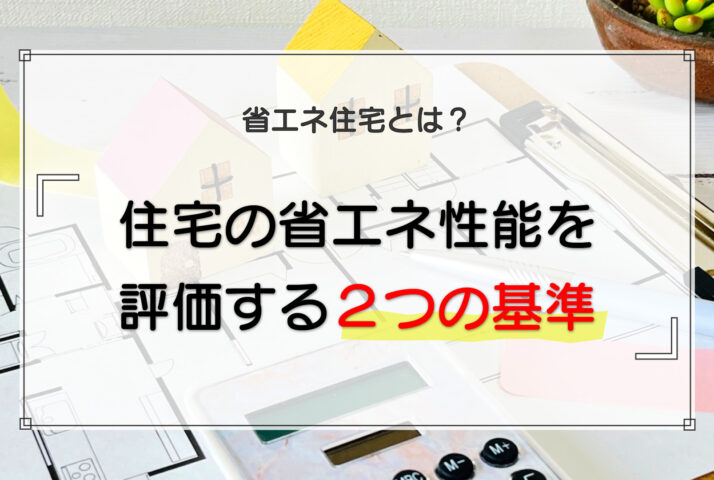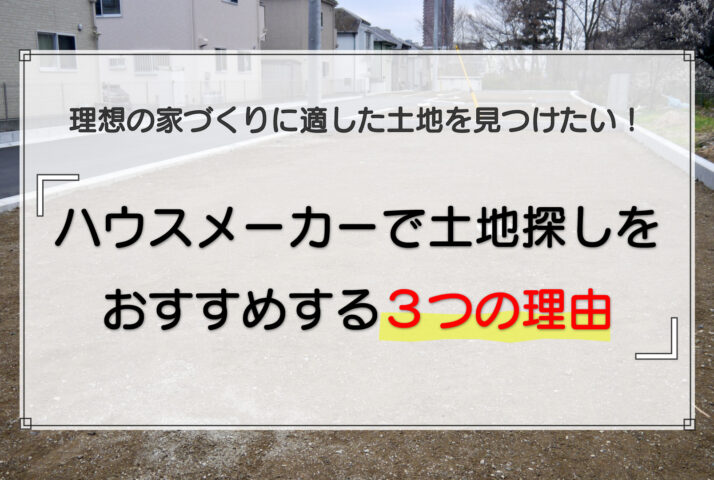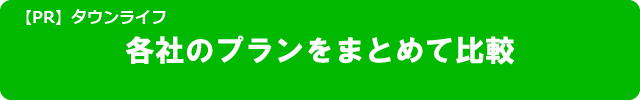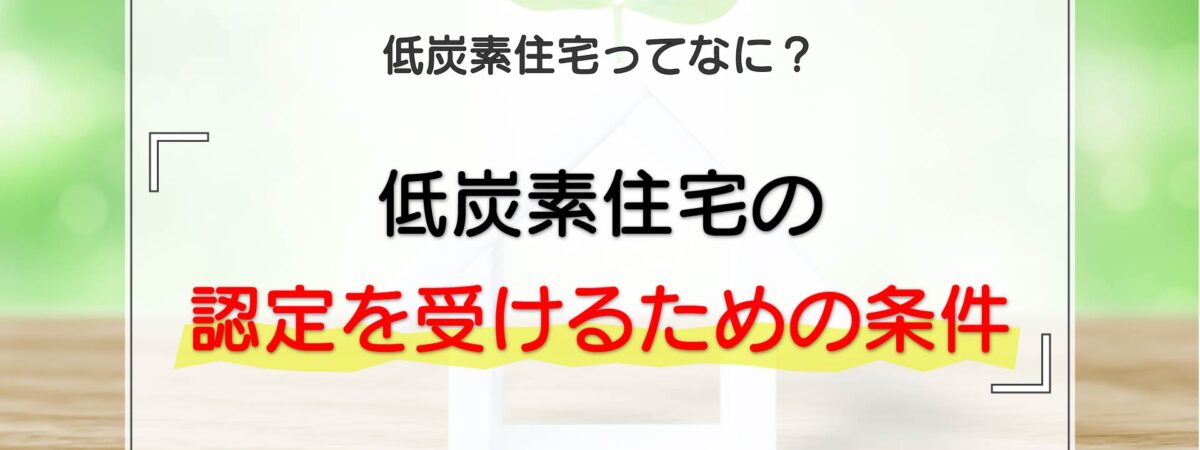
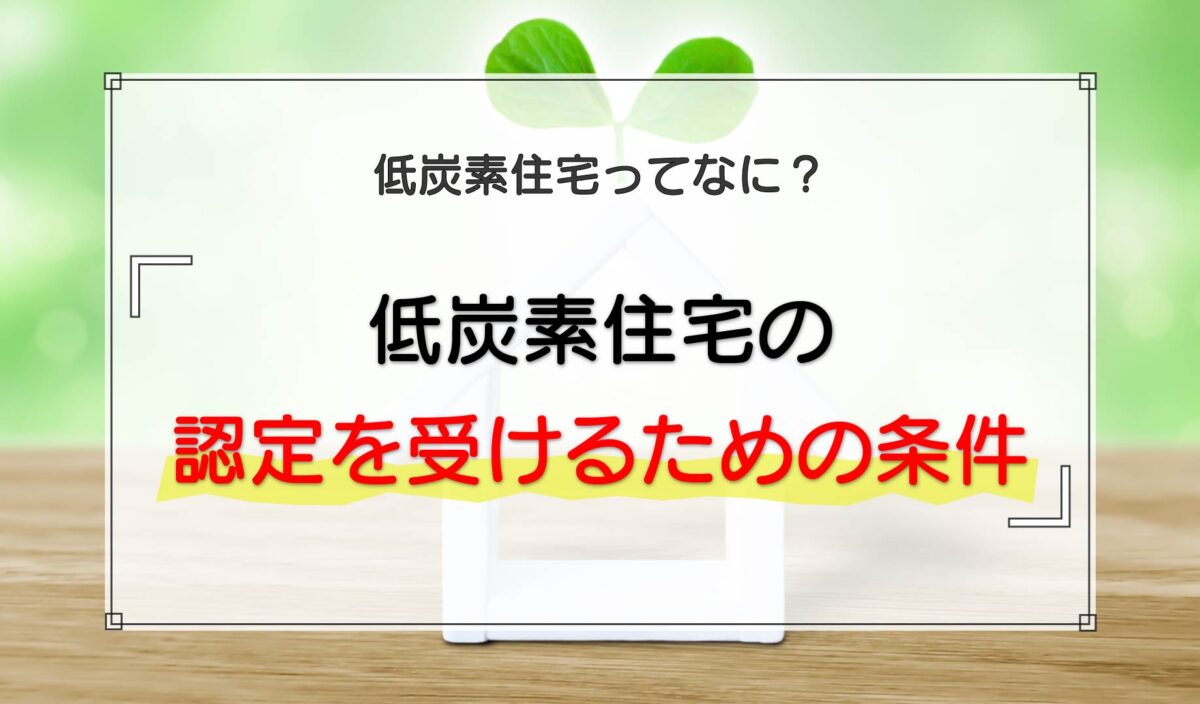
「これから家族が増える」「再来年の4月に子供が入園する」など、家族ごとにタイミングは違えど住宅の購入を検討する方も少なくないでしょう。昨今の家づくりにおいては、住宅性能がトレンドのひとつです。
2020年10月26日、当時の総理である菅総理が「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、住宅においてもさらなる省エネルギー化・脱炭素化に向けた取り組みが加速しているからです。
そのため、ハウスメーカーや工務店などの建築会社は住宅性能を謳った訴求をよく目にするようになりました。
国としても性能の高い住宅の数を増やすべく、さまざまな支援策を講じています。その支援策の対象となる住宅性能のひとつに「低炭素住宅」があります。
そこで今回は、低炭素住宅について掘り下げて解説します。低炭素住宅の概要から認定の条件、受けられる優遇制度を紹介します。よく比較される「長期優良住宅」や「ZEH」との違いについても解説しますので、家づくりで住宅性能にこだわりがある方は、ぜひ参考にしてください。
この記事で学べるコト
- 低炭素住宅の概要がわかる
- 低炭素住宅の認定条件がわかる
- 低炭素住宅で受けられる優遇制度がわかる
- 長期優良住宅・ZEHとの違いがわかる
- 2022年10月以降の変更点がわかる
目次
1.低炭素住宅とは?環境に配慮したエコな住宅

低炭素住宅をわかりやすく説明すると「二酸化炭素の排出を抑えるため、再生可能エネルギー・蓄電池などの設備導入や高い断熱性能などが備わっている環境に配慮したエコな住宅」を指します。
環境への配慮だけでなく、一般的な住宅に比べると導入する設備や断熱性能など、高い住宅性能を有しているため、快適な生活を送るのに適した住宅です。
また、所管行政庁が低炭素住宅として適合した住宅に認定をあたえています。「環境に配慮した住宅ですよ」とお墨付きがもらえるので、仮に売却することになっても物件価値や需要が高く、一般住宅よりも高い売却価格が期待できるでしょう。
2.低炭素住宅の認定を受けるための条件

低炭素住宅は、2012年12月に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(略称:エコまち法)によって定められており、次の3つすべてを満たしていなくてはいけません。
①省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること
②都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
③資金計画が適切なものであること
引用:国土交通省「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」
このように、3つの条件がありますが、もう少しわかりやすく認定を受けるための条件を紹介します。
注文住宅や新築戸建てなどの場合、低炭素住宅として認定を受けるには「低炭素住宅の認定基準をクリアした住宅を建てる」「市街化区域内で建築する」の2つの条件をクリアした住宅を建てなくてはいけません。
低炭素住宅の認定基準は、具体的に次の4つの要件を満たす必要があります。
- 省エネ法で定める省エネルギー基準と比べて、一次エネルギー消費量が▲20%以上の省エネ性能であること(一次エネルギー消費量等級6)
- 外皮性能を誘導基準(強化外皮基準)の断熱性能を確保する(断熱等性能等級5)
- 再生可能エネルギーの設備導入&省エネ+創エネの合計が基準一次エネルギーの50%以上であること
- 低炭素住宅化に資する措置を講じること
低炭素住宅を建てようと考えている方は、上記に該当する家づくりは可能なのか。建築会社に事前確認しておくと良いでしょう。
3.低炭素住宅に認定されると受けられる優遇制度
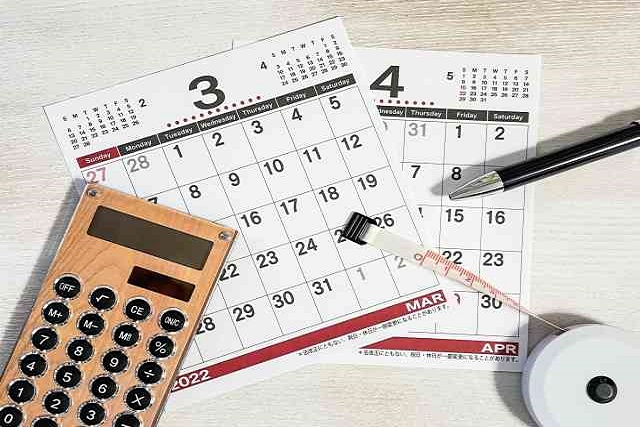
昨今の住宅は、国の政策で住宅性能の向上に取り組んでいます。建築主に低炭素住宅を採用してもらうため、多くの誘導施策を講じています。
低炭素住宅は一般的な住宅と比べて、補助金や減税といった優遇制度の恩恵をうけられます。優遇制度をうまく活用することで、住宅取得にかかわる負担を軽減することが可能です。
低炭素住宅で利用できる優遇制度は次の3つです。
- 子育てグリーン住宅支援事業
- 住宅ローン控除
- 登録免許税の軽減特例
それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
3-1.子育てグリーン住宅支援事業
注文住宅の新築や新築分譲住宅を購入する際に、購入費用の負担を軽減するために創設された新しい制度です。
子育てグリーン住宅支援事業は、省エネ性能の高い注文住宅の新築や新築分譲住宅を購入するときに補助金が交付されます。
低炭素住宅は世帯の条件があり、子育て世帯・若者夫婦世帯の方が対象です。住宅性能の区分に応じて補助額が設定されています。
| 対象世帯 | 住宅性能 | 補助額 |
|---|---|---|
| すべての世帯 | GX志向型住宅 | 160万円/戸 |
| 子育て世帯 若者夫婦世帯 |
長期優良住宅 | 80万円/戸 100万円/戸※建て替え前に居住していた住宅を除却する場合 |
| ZEH水準の住宅 | 40万円/戸 60万円/戸※建て替え前に居住していた住宅を除却する場合 |
低炭素住宅はZEH水準の住宅に該当するので、子育てグリーン住宅支援事業を利用すれば、1戸あたり40万円の補助が受けられます。建て替え前に居住していた住居を除去すれば、20万円が控除額に上乗せされます。
このように、子育てグリーン住宅支援事業を有効活用することで、建築費用の負担を軽減できるでしょう。
ただし、対象要件や手続きの期間など多くの決め事があるため、制度の理解を深めなくてはいけません。
子育てグリーン住宅支援事業について詳しく知りたい方は、子育てグリーン住宅支援事業が創設!住宅取得がおトクになる補助制度を徹底解説を参考にしてください。
3-2.住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅購入もしくはリフォームする際に、所得税や住民税から一定期間の控除を受けられる制度です。
住宅性能に応じて借入限度額が設定されています。低炭素住宅の場合、下記表のとおり控除を受けられます。
| 世帯別 | 期間 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 2022年~2023年 | 5,000万円 | 0.7% | 13年 | 455万円 |
| 子育て世帯 若者夫婦世帯 |
2024年入居 | 5,000万円 | 0.7% | 13年 | 455万円 |
| 上記世帯以外 | 2024年入居 | 4,500万円 | 0.7% | 13年 | 409.5万円 |
「令和6年度税制改正大綱」で、子育て世帯と若者夫婦世帯の借入限度額が2023年の水準に変更となりました。
そのため、低炭素住宅を新築するのが「子育て世帯・若者夫婦世帯」なら最大で455万円。「それ以外の世帯」なら409.5万円の控除が受けられます。
2024年の住宅ローン減税の変更点について知りたい方は、2024年の住宅ローン減税(控除)が一部変更!令和6年度税制改正の大綱からポイントを解説で詳しく解説していますので参考にしてください。
3-3.登録免許税の軽減特例
住宅を取得すると土地や建物の所有者だということを証明するために、不動産登記を行います。この登記をするときには登録免許税が必要です。
登録免許税は「課税評価額×税率」で計算されますが、低炭素住宅の認定を受けている住宅については、次の表のように税率の軽減特例が適用されます。
| 本則税率 | 低炭素住宅 | 一般住宅 | |
|---|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.1% | 0.15% |
| 所有権移転登記 | 2.0% | 0.1% | 0.3% |
※2027年3月31日までの措置
新築の場合、所有者として権利を記録する「所有権保存登記」をしなくてはいけません。所有権保存登記の税率に対して特例措置が適用されます。
たとえば、低炭素住宅を新築するとすると、所有権保存登記にかかる税率は0.1%の軽減特例が適用されます。建物の課税評価額が1,000万円とすると、住宅を取得する際の、1万円の登録免許税が必要です。
一般住宅においても軽減特例が適用されますので、低炭素住宅としての恩恵は小さいですが、登録免許税の軽減特例のメリットは少なからずあると言えるでしょう。
4.よく比較される長期優良住宅・ZEH住宅との違い
住宅性能で言うと低炭素住宅の他に「長期優良住宅」と「ZEH住宅」があります。初めて家づくりをする方にとっては、どの性能にすれば良いのか迷ってしまうでしょう。
そこでこの章では、よく比較される長期優良住宅とZEH住宅との違いについて解説します。
4-1.長期優良住宅との違い
長期優良住宅は、長期使用することを想定して建てられた「長持ちする住宅性能の高い建物」です。低炭素住宅と同様に所管行政庁が認定しています。
長い期間、生活していても問題なく住まいとして使用できるように、構造や設備など厳しい基準に適合した住宅です。
長期優良住宅には次の4つの認定基準が設けられています。
- 構造や設備など長期使用するための措置が施されている
- 快適な生活が送れるように一定以上の居住スペースが確保されている
- 地域に形成される住宅として街並みと調和した配慮されている
- 建築する段階から将来を見据えた補修・点検などの計画をしている
参考:国土交通省「長期優良住宅の認定基準について」
さらに、求めるべき性能として次の9つの項目があり、すべての基準を満たさなくてはいけません。
| 認定の項目 | 内容 |
|---|---|
| 躯体の耐久性 | 住宅の構造躯体が数世代にわたって使用できる |
| 耐震性に優れている | 極めてまれに発生する震度6以上の地震に対しても、損傷レベルを低減できている |
| メンテナンスを考えた設計 | 耐用年数が短い設備配管の清掃・点検・補修・交換など維持管理をしやすくしている |
| 省エネルギー | 断熱性を高めて冷暖房負荷を軽減できるような省エネルギー性能が確保されている |
| ライフスタイルにあわせたリフォームのしやすさ ※共同住宅や長屋などに適用 |
居住者のライフスタイルの変化に応じた間取り変更が可能になっている |
| 将来を見越したバリアフリー対策 ※共同住宅や長屋などに適用 |
共用廊下や共用階段などに十分なスペースが確保されている |
| 居住環境 | 地域に形成される住宅として居住環境の維持および向上に配慮されている |
| 住居面積 | 快適な生活空間を確保するために必要な広さを有している |
| 維持保全計画 | 住宅の建築段階から将来を見据えた定期的な点検・補修に関する計画が策定されている |
長期優良住宅と低炭素住宅では、どちらも「断熱等性能等級5」「一次エネルギー消費量等級6」のZEH水準の住宅です。省エネ性能の高い住宅なので、快適に生活することができます。
ただし、長期優良住宅は認定までにクリアしなけばならない基準の項目が多く、難易度としては「長期優良住宅」の方が高いです。
4-2.ZEH住宅との違い
ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(NET Zero Energy House)の頭文字を組み合わせてできた言葉です。
太陽光パネルなどでエネルギーと創り、省エネ性能の高い設備を導入することで電力消費を抑制、高い断熱性能でエネルギー利用頻度を抑えるといった相乗効果で、生活に必要な一次エネルギーの消費量をおおむねゼロにする住宅がZEH住宅です。
ZEHの認定基準には次の4つの定義があります。
①ZEH強化外皮基準(地域区分1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC 値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値[W/m2K]1・2地域:0.40以下、3地域:0.50以下、4~7地域:0.60以下)
②再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量削減
③再生可能エネルギーを導入(容量不問)
④再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減
引用:資源エネルギー庁「ZEHの定義(改定版)」
上記、4つの定義を満たした住宅がZEHで、一次エネルギー消費量の削減率によって「ZEH Oriented」や「Nearly ZEH」と分類されます。
低炭素住宅は「再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量削減」が条件となるので、簡単にZEH住宅との違いをまとめると「再生可能エネルギー等の設備導入の有無」「省エネ+創エネの合計の基準一次エネルギー消費量削減率」「低炭素住宅化に資する措置しているか」になります。
ZEHについて詳しく知りたい方は、ZEH(ゼッチ)基準の戸建てが当たり前?2022年以降のロードマップから重要なポイントを解説の記事も参考にしてください。
ZEHよりも一次エネルギー消費量削減が少ない「低炭素住宅」は、認定が受けやすく優遇制度も充実しています。
5.2022年10月以降は注意が必要?認定基準の引き上げが予定されています

本記事で紹介したとおり、2022年3月時点の低炭素住宅の認定基準は、たくさんの優遇制度の恩恵を受けられます。しかし、2022年10月に認定基準が引き上げられる予定です。
2021年8月に行われた第6回「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」の資料によると、2022年4月に省エネルギー性能を表した等級に上位等級が創設されます。
これまで、断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級5が最上位でしたが、断熱等性能等級では「等級5(Ua値≦0.60)」、一次エネルギー消費量等級では「等級6(一次エネルギー消費量が▲20%)」が新たに設定されます。さらに2022年10月には、省エネ性能レベルの整合性を図るため、認定基準が見直されます。
認定基準の見直しによって、低炭素住宅や長期優良住宅など、バラバラだった認定基準をZEH水準まで省エネ性能を引き上げて足並みをそろえる動きとなりました。
また、低炭素住宅はZEH基準に加えて、太陽光発電システムなどの設備導入が要件化に見込まれています。さらに一次エネルギー消費量の合計が▲50%以上必要で、ZEH OrientedとNearly ZEHの間ぐらいの省エネ性能が求められることになります。
まとめ
低炭素住宅は、所管行政庁が認定している「環境に配慮したエコな住宅」です。2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、国が今まさに力を入れて導入を促しています。
低炭素住宅の認定を受けるには、次の4つの要件をクリアしなくてはいけません。覚えておきましょう。
- 省エネ法で定める省エネルギー基準と比べて、一次エネルギー消費量が▲20%以上の省エネ性能であること(一次エネルギー消費量等級6)
- 外皮性能を誘導基準(強化外皮基準)の断熱性能を確保する(断熱性能等級5)
- 再生可能エネルギーの設備導入+省エネ+創エネの合計が基準一次エネルギーの50%以上であること
- 低炭素住宅化に資する措置を講じること
2022年にはZEH基準に認定基準が強化され、太陽光発電システムなどの設備導入が要件化されました
建築コストが高騰する昨今ですが、国もこれから新築される住宅の省エネ性能を強化したい狙いがあります。
高い住宅性能を有した住まいでは、快適な生活環境を確保できますので、マイホームを検討される際には、ぜひ、住宅の性能にも目を向けてください。
「どこの建築会社に相談しよう?」
業者選びを始めるなら
各社のプランを無料で比較!
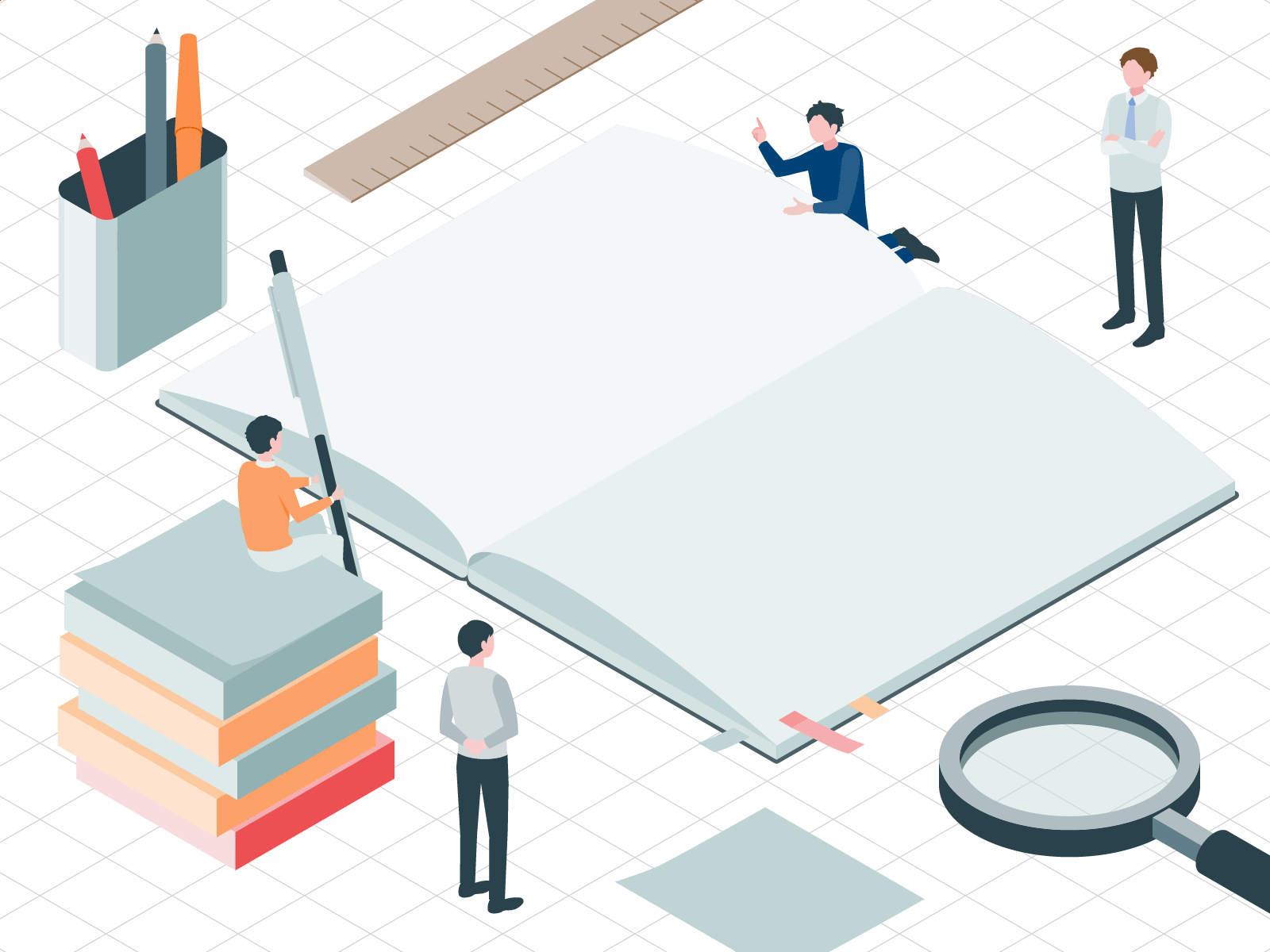
注文住宅は一生に一度の大きな買い物。絶対に失敗したくない!
家族の理想を叶えてくれる建築会社を決められない...
素敵な内観を参考にしてるけど取り入れたいプランがありすぎる!
ひとつでも当てはまるなら、
複数社のプラン比較がおすすめです
家族の理想をカタチにできる注文住宅。
理想を実現するためには、優れたパートナー選びが大切なのはわかる。
だけど、一社一社調べるには時間も手間もかかって効率が悪い、、、
そこで、すきま時間の情報収集で利用してほしいのが
「タウンライフ家づくり」です。
タウンライフ家づくりでは、家づくりで大切な「資金計画」から「間取り」など、あなたの要望にあったプランをまとめて比較できます。
もちろん利用は無料!
提案してくれた企業と契約しないといけない縛りもありません。
これから理想の家づくりを始めるなら、まずは自分にピッタリな間取りプランを把握しましょう。